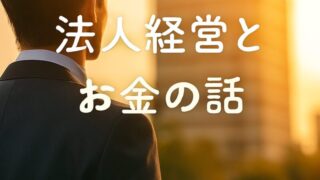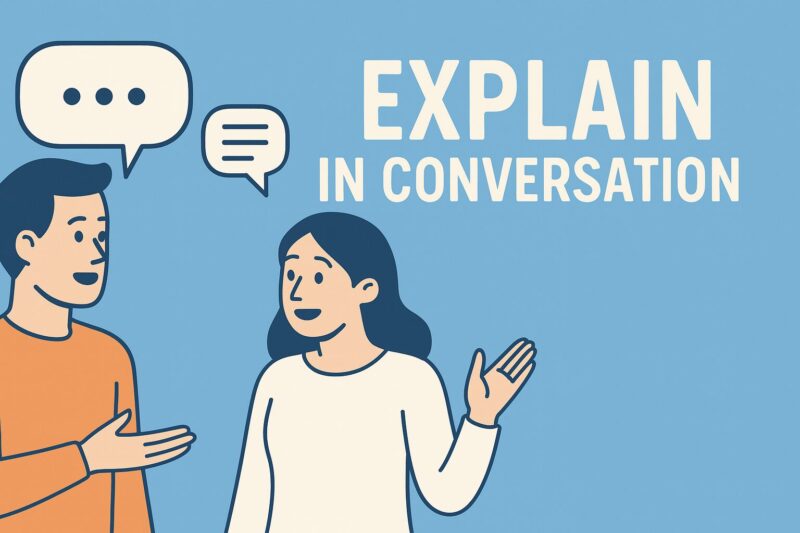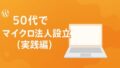『法人化って、結局なんのためにするん?』
最近、あなたの周りでも、個人事業から法人化する人が増えていませんか?『法人にしたらええぞ』と言われても、正直、何がどう変わるのかよく分からない──。そんな疑問を抱えるあなたは、決して一人ではありません。
今回の記事は、FP1級・宅建士の私、ひまわりと、塗装業を営む兄・ゆうたの会話形式でお届けします。『法人化は事業の規模ではなく、働き方の「制度を選ぶ」こと』。この視点から、個人と法人の根本的な違いを分かりやすく解説します。」
最近、まわりが法人にしてるんやけど…
「ひまわり、ちょっと聞いてええか?最近、同業の仲間が次々と法人にしててな。『法人にしたらええぞ』って言われるんやけど、正直よう分からんのや。俺も個人事業でずっとやってきたけど、ほんまに法人ってええんか?」
兄のゆうたが、現場帰りの作業着のまま、缶コーヒー片手にぽつりと言った。塗装業として10年以上個人事業を続けてきた彼にとって、法人化はどこか“他人事”だった。でも、周囲の変化に少し焦りを感じているようだった。
「うん、法人化って言葉だけ聞くと大げさに感じるかもしれないけど、実は事業の規模は関係ないの。大事なのは、“制度を選ぶ”っていう考え方」
「俺が全部責任持ってやってるやん?法人にしたら、責任が軽くなるとかあるん?」
「そういう話もあるけど、まずは“人格”の違いを理解するのが大事。個人事業は、事業と自分が一体。一方で、法人は法務局で登記して**“「会社」という別人格”**を作るの。つまり、兄ちゃんが“個人”として仕事してるのか、“会社の代表”として仕事してるのかで、制度の扱いが全然変わってくるんよ。」
(法人の設立手続きについては、法務省|登記の申請方法についてで確認できます。)
個人事業主と法人の違いを比較
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社など) |
| 法的な立場 | 自分=事業 | 法人格を持つ別組織 |
| 契約・信用 | 個人名義で契約 | 法人名義で契約、信用度向上 |
| 税制 | 所得税(累進課税) | 法人税(定率)+役員報酬に所得税 |
| 社会保険 | 国民健康保険+国民年金 | 健康保険+厚生年金(法人が半分負担) |
| 経費の幅 | 限定的(家事按分など) | 役員報酬や生命保険料など法人経費として幅広く認められる |
「なるほどな…法人にすると、制度の枠が変わるってことか。」
「法人化って“規模が大きいからするもの”じゃなくて、“制度を選ぶ”っていう考え方よ。」
「俺に向いてるか?」──本音のぶつかり合い
「節税ってよう聞くけど、ほんまにそんなに違うんか?でも、俺、現場から帰ってきたらもう何も考えたくなくて。正直、こういう細かいこと考えるのが一番しんどいねん。」
「うん、節税って言葉だけが一人歩きしてるけど、実際は税の仕組みが違う。個人事業は所得税で、儲けが増えるほど税率も上がる。法人は法人税で定率やから、利益が一定以上あると有利になることがあるよ。」
「俺に向いてるかどうかって、どう考えたらええん?」
「それは“事業の目的”と“将来の設計”によるかな。例えば、今後スタッフを雇いたいとか、家族を従業員にしたいとか、事業を引き継ぎたいとか、そういう展望があるなら法人化は選択肢になるし、逆に、ひとりで完結する仕事で、収入も安定してるなら、個人事業のままでも十分かもね。」
「なるほどな…法人化って、ただの形式やなくて、**『働き方の設計』**なんやな。」
「そう。法人化は『制度を選ぶ』ってこと。だからこそ、焦って周りに合わせるんじゃなくて、**『俺は俺のペースで考えたらええ』**ってことや。周りが法人にしてるから不安になるけど、正直、俺はこういう細かいこと考えるのが得意じゃないし、気楽なほうが性に合ってるねん。」
ひまわり「うん。法人化は“目的”があってこそ意味がある。例えば、社会保険に入りたい、信用力を上げたい、経費を柔軟に使いたい、事業承継を考えたい…そういう『制度を活かしたい理由』があるなら、法人化は有効。でも、なんとなく不安だからってだけで法人にしても、手続きや管理が増えるだけで、メリットを感じにくいかもしれないよ。」
4. まとめ:法人化は「制度を選ぶ」という働き方の設計図
法人化は、単なる節税対策ではありません。それは、自分の事業や将来の人生設計に合った**『制度を選ぶ』**という、賢い働き方の設計です。
周りの動きに焦る必要はありません。 まずは「自分はどんな事業を、誰と、どうやって続けていきたいか?」 この問いから、あなたにとって最適な道を探してみてはいかがでしょうか。
【大切なご案内】 この記事は、私自身の経験やFPとしての一般的な知識に基づき、お金や税金の仕組みを分かりやすく解説したものです。しかし、個別の状況によって最適な選択は異なりますし、税法は常に改正される可能性があります。最終的な税務判断は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。この記事はあくまで参考情報としてお役立ていただき、ご自身の判断と責任のもとでご利用ください。