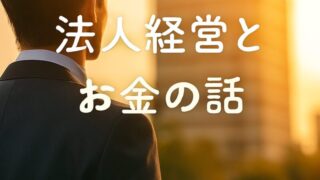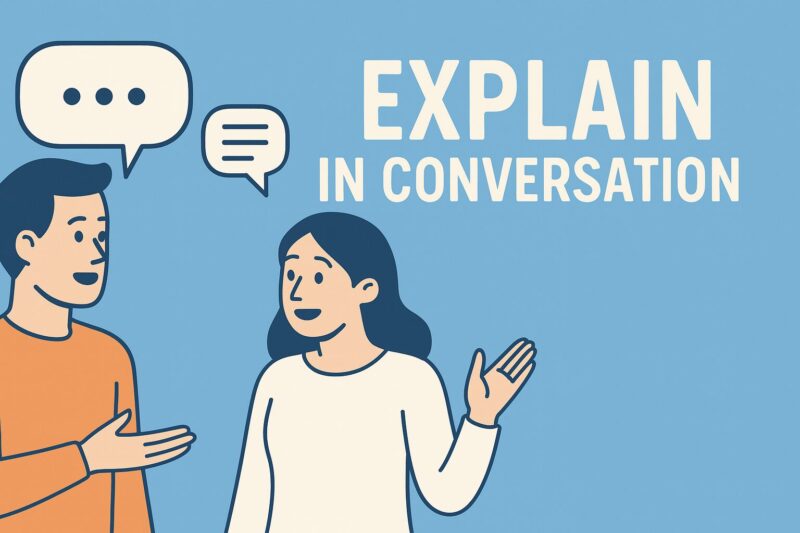──『社会保険料、今月もガッツリ引かれてるな…』
給与明細や確定申告を前に、あなたは「社会保険料、高すぎる!」と感じていませんか?毎月の負担が大きいと感じる一方で、「結局、これって何のため?」と疑問に思う人も多いかもしれません。
実は、社会保険は単なる「負担」ではなく、もしもの時に家族を守るための「保障」です。
今回の記事は、会社員の弟・こうたと、個人事業主の兄・ゆうたとの会話を通して、FP1級・宅建士の私、ひまわりが、社会保険の「負担」と「保障」のバランスについて分かりやすく解説します。
1. 社会保険料、今月もガッツリ引かれてるな…
こうたが、給与明細を見ながらぼやいた。
「社会保険料、今月もガッツリ引かれてるな…手取り、全然増えへん。これって、払ってる意味あるんかいな?」
兄・ゆうたも、現場の休憩中に仲間と話していたことを思い出す。
「法人にしたら社会保険入らなあかんって聞いたけど、あれって結局得なんか?国保のままのほうが気楽ちゃう?」
週末、また家族が集まった。話題は自然と「社会保険の負担と保障」に移っていった。
「会社員って、保険料めっちゃ引かれるよな。」
こうたがぼそっと言う。
「でも、会社が半分出してくれてるんやろ?それってええことちゃうん?」
「たしかに会社が折半してくれてるけど、こっちの負担も十分重いで。年収上がるほど引かれる額も増えるしな。」
ひまわりがうなずく。
「社会保険って、“高い”って感じる人が多いけど、その分**『保障』**も手厚いのよ。医療費の自己負担が3割で済むのも、年金が老後に支給されるのも、全部この制度のおかげなの。」
2. 個人事業主はどうなん?
ゆうたが口を挟む。
「俺は国保と国民年金やけど、正直、保障は薄い気するで。年金も将来いくらもらえるか分からんし。」
「ほんとね。国民年金は定額で、将来もらえる額も少なめ。医療費も、国保は自治体によって違うけど、会社員の健康保険よりは手厚くないことが多いの。」
「法人にしたら、厚生年金と健康保険に入れるんやろ?でも、保険料が高なるって聞いたことあるで。」
「そう。保険料は上がる。でも、将来もらえる年金額も増えるし、医療保障も広がる。扶養の家族も保険に入れられるから、家族全体の安心につながるのよ。」
3. 役員報酬って下げたら保険料も安くなるけど…
こうたがふと気になったように言う。
「そういえば、法人にした人が**『役員報酬を月5万円にして社会保険料を安くしてる』**って言うてたけど、それってアリなん?」
ひまわりが答える。
「そうね、報酬を低く設定すれば、厚生年金や健康保険の保険料は安くなる。でも、将来もらえる年金がその分少なくなるし、傷病手当金も減るよ。」
ゆうたが首をかしげる。
「傷病手当金って、病気で休んだときにもらえるやつやろ?それも報酬に関係あるん?」
「そう。傷病手当金は、報酬の約3分の2が1日あたり支給される仕組みなの。たとえば、標準報酬月額が5万円やったら、1日あたりの支給額は1,000円ちょっとになるのよ。」
「それやと、休んでも生活費にはならへんな…。」
「そうなの。保険料を抑えるのは節約になるけど、**『いざというときの保障』**も小さくなるってこと。年金も同じで、報酬が低いと将来の受取額も減るのよ。」
こうたがうなずく。
「なるほどな。保険料だけ見て“安いほうがええ”って思ってたけど、保障の中身も見なあかんってことか。」
ひまわりが続ける。
「それに、報酬が少なすぎると、毎月の生活にも支障が出るよ。法人にしたら、報酬は『会社からの給料』になるから、生活費としてちゃんと使える額にしておかないと。」
4. 社会保険の『負担と保障』を比較
| 区分 | 保険料負担 | 医療保障 | 年金 | 家族の扶養 |
| 国民健康保険+国民年金 (個人事業主) | 全額自己負担 | 自治体による(3割負担) | 基礎年金のみ | 扶養制度なし |
| 社会保険 (法人・会社員) | 会社と折半 | 健康保険+傷病手当金など | 厚生年金+基礎年金 | 扶養家族も保険対象 |
5. まとめ:社会保険は『入るか入らないか』ではなく、『どう付き合うか』
ゆうたが、少し真剣な顔で言った。
「結局、どう考えたらええんやろな…。保険料は高いけど、入らなあかんもんやし。」
ひまわりがうなずく。
「そう。日本は**『国民皆保険』**の制度があるから、どんな働き方でも何かしらの保険には必ず入ることになってるの。個人事業主と法人の役員では仕組みが違うけど、どちらも“入らなくていい”っていう選択肢はないのよ。」
「なるほどな。やっぱり、保険料だけで判断するんやなくて、**『どんな保障があるか』**を見て考えなあかんな。」
「そうね。法人化を考えるなら、保険のことも一緒に見ておかないと。家族の働き方や将来のことも含めて、バランスを取るのが大事よ。」
「はいはい、何でもバランスバランスね。それがわからんねん。」
ゆうたが少し呆れたように言うと、こうたが笑って言った。
「そらそうやな。でも、そういうの、ちゃんと教えてもらえる人がおるって、ええことちゃう?ひまわりおって助かるわ。」
【大切なご案内】 この記事は、私自身の経験やFPとしての一般的な知識に基づき、お金や税金の仕組みを分かりやすく解説したものです。しかし、個別の状況によって最適な選択は異なりますし、税法は常に改正される可能性があります。最終的な税務判断は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。この記事はあくまで参考情報としてお役立ていただき、ご自身の判断と責任のもとでご利用ください。