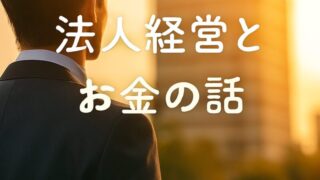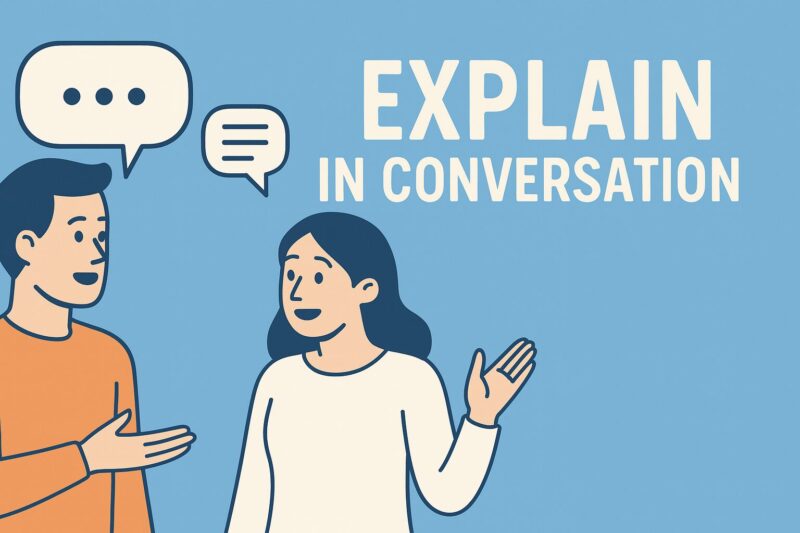──『もし、現場でケガをしたら…』
あなたは、ご自身の仕事における**「万が一」のリスク**について、どれくらい備えていますか?特に、個人事業主の方は、ケガで働けなくなると収入が止まるという不安を常に感じているかもしれません。
今回の記事は、塗装業を営む兄・ゆうたとの会話を通して、現場仕事に欠かせない**「労災保険」の仕組み**と、個人事業主や法人役員が加入する方法について、分かりやすく解説します。
1. この前、脚立から落ちかけてな…
日曜の午後、兄弟3人が近所の喫茶店に集まった。兄・ゆうたは、現場での出来事を思い出してぼそっと言った。
「ひま、俺な、この前、脚立から落ちかけてな。ほんまにヒヤッとしたわ。俺、個人事業やし、ケガしたら収入がなくなるやんか。労災って、法人にしたら使えるんか?」
「それ、気になるな…」と弟・こうたもうなずく。
「俺は会社員やから、労災は会社が入ってるけど、兄ちゃんは自営業やな、どうなるんや?」
妹・ひまわりが、コーヒーをひと口飲んでから話し始めた。
「それね。労災保険は、仕事中や通勤中の“もしも”に備える制度なんだけど、法人や個人事業主でもちゃんと加入できるの。でも、代表者や一人親方みたいに『労働者』じゃない立場の人は、**『特別加入』**っていう特別な手続きをしないと入れないのよ。」
2. 労災保険の一般加入と特別加入の違い
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中や通勤中の事故・病気に対して、治療費や休業補償などを支給する公的制度です。雇用される労働者が対象ですが、法人の代表者や個人事業主も「特別加入制度」を使えば加入できます。
| 加入形態 | 加入対象 | 加入方法 | 保険料負担 | 補償内容 |
| 一般加入 | 従業員(雇用契約あり) | 事業主が手続き | 事業主が全額負担 | 治療費、休業補償、障害・遺族給付など |
| 特別加入 | 個人事業主・法人代表者・一人親方 | 労働保険事務組合を通じて | 自己負担 | 業務災害・通勤災害に対する補償 |
詳しくは 特別加入制度のしおり(中小事業主用)をご確認ください。
3. 家族の未来を考える
「兄ちゃん、うちの子、最近“建築の仕事したい”って言い出してな。この前、現場に連れてってもらったやろ?あれがめっちゃ楽しかったみたいで、工具とか足場とか、目キラキラさせてたわ。」
こうたが、スマホの写真を見せながら笑う。兄、ゆうたが少し嬉しそう。
「ほんまにええ子やで。俺、子どもおらんし、めっちゃかわいくてな。現場の厳しさもあるけど、やりがいはある仕事や。でも、ケガのリスクは常にあるから、気つけんとあかん。」
「嫁は“会社勤めしてほしい”って言うてるけど、本人は現場に憧れてるみたいやねん。」
「それならなおさら、労災のことは家族で知っておくのが大切よ。働き方によって、保障の仕組みが変わるからね。将来、本当に現場に出るなら、親としてちゃんとした備えがあるか、教えてあげておきたいわ。」
「そうやな。俺も現場で何回かヒヤッとしたことあるし、備えはほんまに大事や。」
4. 法人化で広がる選択肢
「ひまわり、俺の事業を法人にしたら、労災はどうなるん?」
「法人にすると、従業員を雇った時点で労災保険の加入義務が発生するの。代表者自身は“労働者”じゃないから一般加入はできないけど、**『特別加入』**を使えば、代表者も労災の対象になるわ。」
「特別加入って、どうやって申し込むん?」
「地域の労働保険事務組合に委託する形になるの。建設業なら、商工会や業界団体が窓口になってることが多いから、まずはそこに相談してみるといいわ。」
「俺もそろそろ法人化、考えなあかんな。現場の仕事は好きやけど、体が資本やし、保障がないと不安や。」
「兄ちゃん、法人にしたら社会保険とかも整うし、労災も特別加入できるんやろ?それって安心ちゃう?」
「せやけどな…嫁は**『個人事業のほうが気楽や』**って言うねん。税理士に頼まんでもええし、書類も少ないし、って。法人にしたら手続きも増えるし、社会保険料も高なるやろって、正直、ちょっと尻込みしてるわ。」
ひまわりが、ゆっくりと話し始める。
「確かに、法人化すると手続きやコストは増えるわ。でも、社会保険に入れることで将来の年金額も安定するし、労災の特別加入もできる。それに、法人にすることで信用力も上がるから、仕事の幅が広がる可能性もあるのよ。」
「信用力か…たしかに、最近元請けの会社から**『法人のほうが契約しやすい』**って言われたことあるな。」
「そういう声があるなら、法人化は前向きに検討してもいいと思うわ。もちろん、奥さんの“気楽さ”も大事だから、よく家族で話し合って、どこまでを法人にするか、どこを個人で残すかって。」
「なるほどな…全部をガラッと変えるんやなくて、段階的にってことか。」
「そう。例えば、法人で現場仕事を請け負って、個人事業で副業的な仕事を続けるっていう形もあるわ。働き方に合わせて、制度を組み合わせるのがポイントよ。」
「うちも、嫁は“会社員が安定”って言うけど、子どもは“現場で働きたい”って言うてるしな。家族の考え方って、ほんまにそれぞれやな。」
「だからこそ、制度を知って、選べるようにしておくのが大切なのよ。知らんままやと、『選べる』ことすら気づかへんからね。」
5. まとめ:労災保険は『自分と家族を守る』ための安心設計図
労災保険は、会社員だけのものではありません。個人事業主や法人役員も、制度を知り、適切に活用することで、自分自身の、そして大切な家族の万が一に備えることができます。
「もし、明日働けなくなったら、どうする?」この問いから、あなたと家族が安心して働き続けるための備えについて、話し合ってみてはいかがでしょうか。
【大切なご案内】 この記事は、私自身の経験やFPとしての一般的な知識に基づき、お金や税金の仕組みを分かりやすく解説したものです。しかし、個別の状況によって最適な選択は異なりますし、税法は常に改正される可能性があります。最終的な税務判断は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。この記事はあくまで参考情報としてお役立ていただき、ご自身の判断と責任のもとでご利用ください。