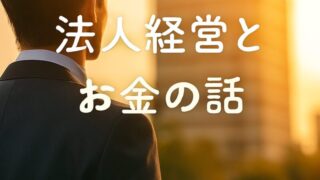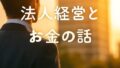(FPが解説|資産寿命を延ばすための実践設計)
はじめに:90歳まで生きる時代、足りるお金、足りないお金
FPひまわりです。
「老後の備えは十分」と思っていても、寿命の延びとインフレが進む中では、計画の見直しが欠かせません。
厚生労働省の簡易生命表によると、2024年の女性の平均寿命は87歳を超え、男性も81歳を超えています。
つまり、90歳まで生きる前提でのライフプランを考える必要があります。。
この“長生きリスク”とは、老後が長くなることで、
・資産が想定より早く減る
・医療・介護費が増加する
・インフレで実質購買力が下がる
といった複合的なリスクが発生します。
ここではFP1級の観点から、資産寿命を延ばすための3つの防衛策を体系的に解説します。
資産の「使い方」を設計する:可視化とシミュレーションが基本
老後資金の不安の根本は、“漠然としていて、足りるのか、足りないのか、はっきりとわからないところにあります。
だからこそ、まずは資産を「見える化」し、シミュレーションで寿命との整合性を確認することが大切です。
たとえば次のような前提を立てます。
- 手持ち金融資産:2,000万円
- 年金収入(月):20万円
- 生活費(月):25万円
- 運用利回り:年1.5%(インフレ率1.0%を控除後)
- 取り崩し開始年齢:65歳
この場合、年間の不足額は約60万円。
単純計算で資産寿命は約33年ですが、実際は利回りや物価上昇を考慮すると85~88歳時点で資金が尽きる可能性が高い。
だからこそ、“定期的な見直し”が不可欠です。
FP実務では、**取り崩し率(withdrawal rate)**を3〜4%程度に抑えると、資産の長期持続性が高いとされています。
生活費に占める年金割合を増やす、もしくは支出をコントロールしてこの水準を維持できれば、長生きリスクを大幅に軽減できます。
「年金+α」の収入をつくる:インカム構造を設計する
資産を減らさないために最も有効なのが、定期的なインカム(収入)をつくることです。収入の入り口を増やします。
具体的には次のようなものがあります。。
| 収入源 | 期待利回り | リスク | 流動性 |
|---|---|---|---|
| 公的年金 | 約2〜3%相当(物価連動) | 低 | 低 |
| 国内配当株・ETF | 年3〜4% | 中 | 中 |
| REIT・不動産収入 | 年4〜5% | 中高 | 中 |
| マイクロ法人役員報酬 | 年60〜120万円目安 | 中 | 高 |
| 副業(オンライン) | 不定 | 中 | 高 |
ここでのポイントは、“取り崩さずに暮らせる構造”を作ることです。
年金+投資配当+法人収入の合計が生活費を上回れば、資産は減らず、むしろ再投資で増えていきます。
また、法人を設立している場合は、役員報酬を年60万円程度に設定することで社会保険料負担を最小限に抑えつつ、事業経費で老後支出を圧縮する戦略も有効です。
(具体的な報酬設定は税理士への確認が必要)
固定費を見直す:「キャッシュフローの引き算」は最強の防衛策
FPの観点では、可処分所得の最大化こそが資産防衛の基盤です。使えるお金を多くしようということです。
固定費を削減することで、同じ収入でも“長く持つ”構造を作れます。
見直しの優先順位は以下の通りです。
- 通信費(格安SIM・不要オプション解約)
- 生命保険(過剰保障・貯蓄型の再評価)
- 住宅ローン(金利交渉・繰上返済シミュレーション)
- サブスク・車維持費(使用頻度の可視化)
特に保険は、老後に不要な保障を抱えたまま保険料を払い続けるケースが多いです。
「死亡保障→医療・介護・生活保障」へシフトし、保険を“守り”から“使えるもの”に変える発想が重要です。
まとめ:「長生きリスク」は設計でコントロールできる
長生きリスクとは、「お金が尽きること」ではなく、運用や取り崩しのルールを整えないことです。
次の3ステップを継続的に実践すれば、人生100年時代でも安心して暮らせます。
- 資産の使い道を具体的に数字で確認する。
- 年金だけに頼らない収入プランを作る。
- まず、固定費を見直して支出を整理する。
老後の安心は、“お金の多さ”ではなく“お金の流れの設計力”で決まります。
今日から1時間、自分のキャッシュフローを見直してみましょう。
それが、最初の資産防衛策です。
注意事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、最終的な判断は税理士・社労士などの専門家にご確認ください。